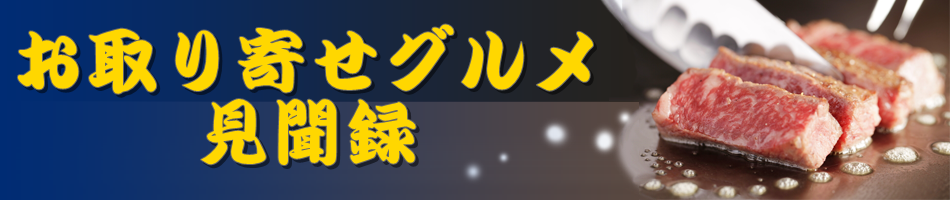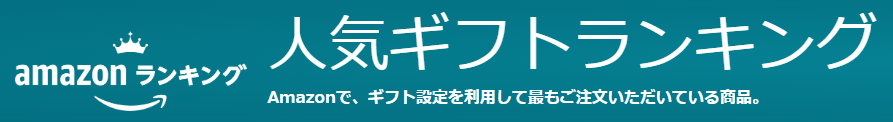[PR]
「高知の名酒『美丈夫』を創る濱川商店 – 超軟水が生み出す最高の純米酒と銘杜氏の情熱」
日本酒通が選ぶ至極の一杯 日本酒 地酒 高知 濱川商店(浜川) 美丈夫 特別本醸造 1800ml 1梱包6本まで ショップ:FELICITY 地酒
価格:1,980 円
|
目次
美丈夫: 高知が誇る酒造りの逸品
高知県東部に位置し、木材の集積地として知られた田安町。
この地に明治37年(1904年)、濱川商店が誕生しました。
この商店は、先代がこの地のやわらかな水を活かして酒造りを始めた「美丈夫」という名の日本酒で有名です。
「美丈夫」は、その洗練された味と品質で多くの人々に愛されています。
今回は、この「美丈夫」の魅力について詳しく見ていきましょう。
高知の自然と調和する酒造り
濱川商店が位置する高知県は、黒潮が育む豊かな自然環境に恵まれています。
特に、地元の海で獲れる鰹を始めとする多くの新鮮な魚と、「美丈夫」は相性が抜群です。
「飲み飽きしない」と評されるそのキレの良い味わいは、地元の人々だけでなく、多くの日本酒ファンに好まれています。
この背景には、高知県の自然と調和する酒造りのスタイルがあります。
日本酒造りには、「米」「水」「杜氏の技」が重要な要素とされていますが、濱川商店では、これらすべてにこだわりを持って取り組んでいます。
このこだわりにより、「美丈夫」はただの日本酒ではなく、高知県を代表する銘柄としてその名を馳せています。
最高の酒米へのこだわり
「美丈夫」の品質の高さは、その原料である酒米へのこだわりにも見られます。
「最高の米で最高の日本酒を造りたい」という思いから、兵庫県産の山田錦が厳選されました。
特に、最高級の特A地区である兵庫県東条の田んぼで収穫される山田錦を使用しています。
また、地元高知県で契約栽培される「吟の夢」、愛媛県産の「松山三井」など、各地域の特性を活かした米による醸造にも力を注いでいる点が、「美丈夫」のユニークさを際立たせています。
これらの米の特性を深く理解し、それぞれに合わせた醸造法を模索し続けています。
超軟水がもたらす特別な味わい
日本酒の造りにおいて、水の質はその味わいを大きく左右します。
「美丈夫」の特徴の一つは、高知県の超軟水を仕込み水として使用している点です。
この軟水は、魚梁瀬地区甚吉森を源とし、奈半利川の伏流水を使っています。
軟水は、主に酒の発酵過程において、微生物の活動を緩やかに進める効果があります。
この特性が、「美丈夫」のほどよい辛さの中に感じられる甘みや、口当たりの滑らかさを実現しています。
また、酸味と米の旨味が調和し、爽やかな甘さが広がるのも、この超軟水のおかげです。
さらに、この水は「美丈夫」に独自の個性を与え、多くの日本酒愛好家に好評を得ています。
杜氏の巧みの技と情熱
濱川商店で「美丈夫」の造りを担うのは、小原昭氏という杜氏。
この杜氏の経験と知識により、「美丈夫」は独自の味わいを持つ酒として進化を続けています。
小原氏は、超軟水がいかに日本酒の仕上がりに影響を与えるかを熟知しており、水の特性を最大限に活かした酒造りを心掛けています。
「美丈夫」の清らかで、しかし芯の通った味わいは、小原氏の言葉通り「飲むが易し、造るは難し」という理念の賜物です。
今後も水の特性を生かしつつ、その短所を補い、長所を伸ばすために試行錯誤が続くことでしょう。
「美丈夫 特別本醸造」の風味とバランス
「美丈夫 特別本醸造」は、愛媛県産の「松山三井」を60%まで精米し、濱川商店ならではの技術で醸されています。
このお酒の大きな特徴は、控えめで穏やかな吟醸香と、滑らかな口当たりです。
また米の旨味や酸味がじんわりと広がり、さわやかな甘みを感じさせます。
適度な辛さと、しっかりした旨味のバランスが絶妙であり、甘味が強すぎないため飲み飽きしないのがこの酒の魅力です。
冷やしても、お燗にしても楽しめるこの酒は、さまざまな料理との相性もよく、その多様な楽しみ方が多くの酒愛好家を魅了しています。
日本酒度は+5、酸度は1.2、アルコール度数は16%と、バランスの取れた一品です。
まとめ: 美丈夫の魅力を味わう
「美丈夫」は、その土地の恵みと職人の技が一体となった、まさに芸術品とも言える日本酒です。
高知の自然環境を最大限に活かし、その土地でしか成しうることができない味わいを実現しています。
清らかで品のある味わいにもかかわらず、親しみやすさもあるこの日本酒は、飲み手の生活に溶け込むように楽しむことができます。
濱川商店のこだわり抜いた米、厳選された水、そして杜氏の情熱。
これらが組み合わさり、『美丈夫』は高知だけでなく日本全国、さらには世界中の日本酒ファンにその存在を知らしめ、愛され続けています。
この日本酒のもつ力強さと繊細さを、ぜひ一度味わってみてください。
きっとその洗練された味わいが、皆さんの日本酒に対する見方を大きく変えてくれることでしょう。
ショップ:FELICITY 地酒
価格:1,980 円
|
関連記事
魅惑の地、新潟から贈る絶品「久保田」飲み比べセット
日本酒好きの皆さんにとって、ふるさと納税とは地元の特産品を味わうという喜び以上のものを提供します。
中でも、朝日酒造株式会社... 酒類 |
日本酒ファン必見!新潟銘酒のきき酒飲み比べセットの魅力に迫る
日本酒を愛する人々にとって、新しい味わいを探求することは大きな楽しみの一つです。
今回ご紹介するのは、そんな日本酒... 酒類 |
魅力的な日本酒セット:花春酒造の純米酒セット
日本酒のファンなら一度は耳にしたことがあるであろう、福島県の名門蔵元、花春酒造。
彼らが提供する最新の日本酒セットが登場しました。
... 酒類 |
導入: 日本酒を楽しむ極上の選択
日本酒。
暖かい座敷に家族や友人と集い、冷たい風を感じながら、ゆっくりと味わう。
そんな日本の風景が、頭に浮かびます。
特に、寒い季節を迎えると... 酒類 |
日本酒ファン必見!秋田の名門蔵「八重寿銘醸」の料理酒
日本酒の世界は、その地域ごとに異なる風味と魅力があります。
特に秋田の日本酒は、その深い味わいと伝統に裏打ちされた品質で、... 酒類 |